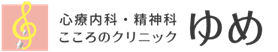日記
2013年3月26日
糟屋医師会鬱病かかりつけ委員会
H25年4月2日に久留米大学精神科教授、内村先生をお招きして、鬱病かかりつけ委員会が行われます。
自殺者を少しでも減らそうという、医師会の取り組みです。
鬱病の患者様は、約半数は医療期間を受診せず、40%は精神科、心療内科以外の科、多くは内科を受診すると言われています。
内科の患者様の約10%~20%は精神疾患の患者様と言われ、鬱病を精神科、心療内科以外の先生方に良く知っていただくことが必要なのです。
①内科、小児科;不眠、原因不明の倦怠感、易疲労感、食欲不振、頭痛、嘔気、口渇、熱発、多汗等
②耳鼻科;難治性の眩暈(浮動性)、耳閉感、味覚の低下等
③整形外科;脳外科、神経内科;原因不明の痛み、痺れ等
が科別に多いと思われます。
2013年4月1日
強迫性障害
強迫性障害とは
Ⅰ;強迫性障害とは
①強迫観念;そこまで気になるはずの無い、或いはどうでも良いはず(自我違和性)の思考、衝動、イメージが、頭に度々浮かび消去し難いことを強迫観念と言います。
②強迫行為;強迫観念に駆り立てられて、その不安を消去や防御する為に行う反復行動を強迫行為と言います。
の少なくともどちらかがある場合を強迫性障害と言います。
強迫性障害の診断
①根本的に困難な状況に置かれれば、人は何度も不安を解消とする行為や防衛行為を行うものです。只、その置かれた状況の困難さとそれを解消しようとする行為、防衛行為の質や程度、頻度が困難さが非相応で過剰なものを根本的に強迫性障害と呼びます。
②置かれた困難の現実性を過剰に深刻さを伴って歪める精神疾患が基礎疾患として存在するならば、当然のごとく強迫性障害或いは強迫性障害様の症状(強迫スペクトラム)が起こり得るものと考えます。
③何故、強迫性障害或いは強迫性障害様の症状(強迫スペクトラム)という語句を使用するかというと、強迫性障害は様々な精神疾患を基礎に発症していることが多く、厳密に強迫観念、強迫行為の有無だけでは診断し難い為です。
④換言すれば、強迫性障害は一側面から見た状態診断であり、この診断が治療に直結することは少なく、治療が困難となることが多いのです。
これは、その内にホームページに掲載いたします。
2013年4月7日
糟屋医師会鬱病かかりつけ委員会
糟屋医師会鬱病かかりつけ委員会(H25年4月2日)
久留米大学精神科教授の内村先生をお招きして、ご講演をしていただきました。
司会は御学友の堤会長にしていただきました。
内科を受診される患者の10~20%は鬱病(軽度の鬱病も入れると)の患者である。
自殺者は毎年3万人前後。
この為、精神科と他科の連携が非常に重要である。ということでした。
久留米ではソーシャルワーカーが他科の医療機関を頻回に訪問して連携を取ったということでした。
糟屋医師会ではこれが可能か検証が必要です。
精神科と他科(特に内科、産婦人科、耳鼻科、整形外科が重要)の連携をどのように密にしてゆくかが一番の問題です。