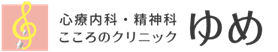日記
2013年10月20日
高機能広汎性発達障害(心の理論と感情理解障害の理論)
心の理論と感情理解障害の理論
高機能広汎性発達障害の不適応の克服方法
不適応場面での克服方法は、現場で周囲の意見を取り入れて(相互理解)或いは推測して、自分を修正するのではなく、読書、講演等の一方的理解に於いて克服する傾向にある。
対人関係における自己表現の困難さ、他人の思考推察能力の低下(客観性に於ける柔軟性の欠如=間主観性の障害)に於ける自信の低下を表している。
これらに心=思考の障害が関与しているという説が心の理論である。
これに対して感情理解の障害は身体表現の読解障害と言われる。
感情理解の障害は身体表現の読解障害と言われる。
これには、思考と感情は表裏一体であり不可分のものであり、「感情」は直観的イメージではあるもののその「感情」を言語で理解し分類する過程で思考を伴うのが必須であり、思考障害がつまり間主観性の障害が換言すれば、客観性=自明の理の歪が関与していると考えられる。
この間主観性=客観性=自明の理は発達すべき最重要な発達課題であるが、これが障害されることにより、主観の場面安定性が担保されない。対人関係、社会性が損なわれることは容易く推測される。
又、客観性=自明の理の障害(自明性の障害)は主観に於いてもその連続性に支障が出現するはずであり、様々な場面(対人関係以外の)における思考能力の低下、理解力の低下の存在が推測される。
重症度の程度はこの客観性=自明の理の障害(時によって、ストレスによって変化)の頻度、範囲によるものと考える。
これら、間主観性~自明性の喪失~客観性の歪は正に統合失調症の中核理論でありPDDが統合失調症の一表現型であると推測することを否定出来ないものと考える。
2013年10月25日
高機能広汎性発達障害(中枢性統合の弱さと執行機能の障害)
高機能広汎性発達障害(中枢性統合の弱さと執行機能の障害)
【1】中枢性統合の弱さ
中枢性統合は入力される情報の共通性、普遍性を見出し、その特性を意味づけし分類、パターン化することである。これは包括的情報処理である。
この為、子細な情報処理=局地的情報は包括的情報処理に内包され包括的情報として処理される。
これらは自然な自明性の喪失や間主観性の喪失、客観性の歪により十分に説明できる。
自明性の喪失や間主観性の喪失、客観性の歪により1+1=2という基本的公式が時に脱落するならば、ありとあらゆる公式=普遍性=特性に付与された意味は恐ろしいことに変性してしまう。勿論これは統合失調症の中核症状であるが。
こうなると、その場での狭い情報処理=局所的情報処理のみが起こり、自己の安定感は失われる。
この為に普遍性、安定性を保持しようとして強迫行為、強迫観念が起こる。
又、安定感、普遍性の残存する部分(狭い範囲の興味)に於いての行動が優先されるため、狭い範囲内の常同行為、パターン化行動が起こる。
局所的情報処理を頻回に又、多くの時間せざるを得ない為子細な部分への意味づけは亢進すると思われる。
【2】執行機能
執行機能とは
①認知的柔軟性。
②優勢であっても、無関係な反応を抑制する事。
③経験から原則を引き出すこと。
④必要な情報と不必要な情報を選別する。
⑤自分の望む目標とそれを実現するのに必要な手順を頭に入れておくこと(ワーキングメモリー)。
これらの執行機能は中枢性統合の存在が必須である。
【3】中枢性統合の弱さと執行機能の障害
中枢性統合の障害により入力情報に対する認知も歪み、認知したとしても自分固有のものとして情報を自己矛盾のない安定化した統合が出来ない。
これは「経験する自己」の欠如とも言え、更に自己存在の時間的連続性を揺るがすものと言える。
執行機能は当然に障害され、自己目的、目的的行動の一貫性、及び実現は障害される。これらが頻度、量ともに多くなれば、自己表現、自己主張、自己実現が困難となり、自信を失い、引き込もることも容易に推測される。
中枢性統合の障害、執行機能の障害は自我意識障害を引き起こす可能性を示唆する。
これら、自明性の喪失、間主観性の喪失、客観性の歪に基づく諸症状は後天的、思春期以降に生じた自己機能低下と言われることがあるが、統合失調症も発達障害も共に遺伝的なものであり、統合失調症とPDD等の発達障害を発症時期で区別することは不可能であり病態として全く同じである。
これは統合失調症の診断が妄想・幻覚優位に診断されていることが原因であり、自明性の喪失、間主観性の喪失、客観性の歪、自我意識障害に基づく診断に変更すべきことを示唆している。
2013年11月3日
主現実と隣接現実
主現実と隣接現実
①客観的で他者と共感しあえる世界→主現実
主観的、自己中心的世界→隣接現実という。
②間主観性を時に失うPDDは主現実よりも隣接現実が支配することが多い。
③又、自明性の喪失、客観性の歪を時に呈すため、情報処理能力に欠け、自己中心的、場当たり的処理を行うため、その場の感情に支配される不安定な世界に存在する。
④安定性のある自己発達が困難で、過去の弔わしい主観的体験、感情に囚われる。時間的な安定性、時間的自我同一性に欠ける。
⑤安定感に欠ける世界、自己を持ち、生き生きとした充足感を持てないこともある。
⑥隣接現実はモザイク状であり、関連性の薄い現実の集合体の為、これを保持するためには記憶を増強させるか、強迫的に想起を繰り返すか等、保存する必要がある。
⑦客観性が低下する為主観、客観の区別が困難になることがあり、認知対象である物、事象共に心的距離を保てない。