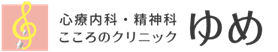日記
2013年11月10日
PDD型自己の特徴
PDD型自己の特徴
PDD型自己は不完全な間主観性~客観性の歪により対人関係に於いて、適切な距離を確保出来ない。
対人関係に於ける距離は、その場の関係を適切に把握することが基本的に重要である。
自己を取り巻く環境の分析、把握が時に困難となれば自己中心的分析に基づく不安定な自信の無い判断を結論づけなければならい。
こうして、ある時は身勝手な、ある時は悲観的、被害的な、距離感の不安定な分析に帰結し、それに基づいた行動をとることとなる。
PDD型自己の特徴とする、不安定な主観的自己は全ての事象で認められるわけではない。
未熟な間主観性~客観性の歪は特にストレス時(トラブルがあった際や、大きな環境の変化等)に特に著明に露呈する。
この為、ストレス対応能力は低い傾向にあると言える。
特に、幼児期、学童期にそのストレスに大きく、頻回に暴露させることによって、主観的自己はその不安定な傾向、悲観的、被害的自己の特性を顕著にしてゆく。
この悲観的、被害的自己が顕著になると自我全体、性格特性を修飾し、ストレスの少ない場面でもこの特性が表現されやすくなる。
又、この特性が頻回に外部に表現されれば、不本意なことではあるが、外部からの自己否定的表現がフイードバックされる。
フィードバックに対する自己の修正は客観性の歪により、やはり困難で、悲観的、被害的自己は歪んだ客観的妥当性を強化する。
このような悪循環は自己評価を不当に低下させ、自己表現を困難にして、積極的人間関係構築、社会性をスポイルする。この悪循環の漂着先は引き篭もりである。
2013年11月17日
解離性同一性障害(多重人格障害)
解離性同一性障害(多重人格障害)
【1】多重人格障害の診断基準
①2つまたはそれ以上のはっきりとした他と区別される同一性、又はパーソナリティ状態の存在。
②これらの同一性、又は、パーソナリティ状態の少なくとも2つが反復的に患者の行動を統制する。
③重要な個人的情報の想起が不能であり、それは普通の物忘れで説明できない程強い。
④この障害は物質、または他の一般的身体疾患の直接的な生理学的作用によるものではない。
【2】多重人格障害患者の病識
多重人格障害患者は人格の交代や健忘をしっかりと意識することは少ない。
これは、多重人格障害が人格の統一性の障害(自我意識障害)
を引き起こし、時間的にも空間的にも自己の存在が不完全で不安定になるからである。
自分の時間的、空間的同一性を確保できなければ自分を確実に意識できない、客観視できないのである。
【3】不安定で病的な防衛機制
多重人格に於ける人格は不完全で不安定なものであり、その人格を完成度の高いものとすることはその本質より不可能である。
この、不完全な人格が、ある程度まとまった行動を起こす為には、他の人格の助けを借りなければならないことは多い。
従って、適応的行動を起こす際には、人格間の疎通性、協力が必要となるため、本来人格を分散させることにより精神的安定を図ろうとする(病的防衛機制である)多重人格化に逆行することにもなり多大なエネルギーが必要となる。
このことからも、多重人格化は究極の防衛機制(病的)と言える。
2013年11月22日
解離性同一性障害(多重人格障害)
解離性同一性障害(多重人格障害)
自我脆弱性の原因
PTSDで解離、多重人格化することはよく知られているが同じ強烈なストレスを受けても必ずしもこのような病的防衛機制をとることが多い訳ではない。
多重人格化する要因として、最も大きいものはやはり個人の病的自我脆弱性が考えられる。
例えば、統合失調症の患者の場合、自明性の喪失、間主観性の喪失、客観性の歪により、ストレスを受けた際、過度に悲観的に被害的に捉える。且それが長期間に渡ることになる。
このことは鬱状態を悪化させ、更に認知機能の低下を招く悪循環に陥る。
何かストレスを受けた際に、人一倍敏感に捉えPTSDとして成立し易くなるどころか、解離しやすくなるのである。
又、自明性の喪失、間主観性の喪失、客観性の歪により時間的、空間的同一性を失い「現実感がない」「自分が自分でない」という離人感、自我意識障害を生じる。
自我意識障害自体が既に解離していることであり、人格を分散化させてストレスに対応しやすい素地を持っていることになる。
双極性障害は私見では、自明性の喪失、自我意識障害を合併する症例が多いと思う。
又、基本的に鬱状態、躁状態の交代があり、この真反対の状態変化は「自分が一つでないようだ」と患者に言わしめるように、人格の変化を意識し易い疾患であるとも言える。
このことは、自我意識障害を呈す疾患は原則的に解離、多重人格化しやすい人格の脆弱性を持ち合わせており、統合失調症、双極性障害は代表的であると言える