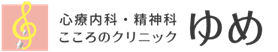日記
2014年4月6日
認知行動療法
3)自己教示法
今日は大丈夫、以前より楽と出来るだけ安易に考える方法であり、自己暗示する方法である。
4)自己強化法
パニック発作が少しでも改善したと思える場合に、自分を褒める方法である。おいしい物を食べたり、自分の欲しい物を購入(常識の範囲内で)したりして報酬を設定するのも良い。
5)思考中断法
悲観的思考は一旦始まると中断することは困難な傾向にある。
この悪循環に気づき、これを中断する方法である。
人と話をする
部屋から外へでる
ゴムで手首をパチッと刺激したり、体を抓ってみたり
絵を描く、考えをかく
歌を歌う
走ったり、スクワットしたり
息を止める
数を数える
等、を行ってみる。
2014年4月13日
認知行動療法
パニック所外の認知行動療法
6)認知再構成法
自動思考(ある条件下で行う歪みのあるパターン化された思考)に対して、歪を修正しようとする試みである。
①自動思考の根拠を考える(その根拠と結果への反証を探す)。
②どんな結果が待っているかを考える(そこまで悲惨な結果なのか、そこまで困ったことが起きるのだろうか)。
③別の考え方をしてみる(結果として柔軟な現実的な思考は何かを考える)
これにより広場恐怖や、予期不安の改善を期待できる。
例えば、電車に乗るとパニック発作が起こるに違いないと考える広場恐怖に対して、「パニック発作が起こったとしても死ぬことはないし、気が狂うこともない、苦しくなれば次の駅で下車すればよいではないか、その後どうしても目的地に到着しなければならなければタクシーで行けばよい」と考える。
2014年4月20日
統合失調症の認知機能障害
統合失調症の認知機能障害
統合失調症の記憶障害
記憶の種類
①一次記憶(短期記憶、ワーキングメモリ―)
比較的短時間記憶に留められるがやがて忘れられる記憶。
忘れ去ることは日常生活上の一つの適応能力と言える。
②二次記憶(陳述記憶、エピソード記憶、手続き記憶)
一次記憶が短期の記憶であり、短期のみ必要とされる記憶であることに対して、二次記憶は長期に必要とされ(想起)、情報処理される記憶である。
これは膨大な情報を自分にとっての必要性、特徴を整理して、保存しつつ必要に応じて使用できるようにする機能である。
単語の意味の記憶(陳述記憶)、印象深い出来事の記憶(エピソード記憶)、手続き記憶(一連の動作を覚える記憶)である。
③長期記憶
長期に渡って記憶を保持し、これを活用する能力である。