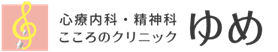日記
2014年4月27日
統合失調症の認知機構障害
統合失調症の認知機構障害
①統合失調症に於ける一次記憶(ワーキングメモリー)障害
今、そこの状況に於ける「誰が何をどうして、自分はこう感じた」という五感の情報である。これには単純な情報から複雑な情報まで,様々な一時的記憶である。
根本的には直ぐに消去(忘れ去られる)される記憶ではあるが、統合失調症は一部分ワーキングメモリーの消去が困難となることがあり(被害的記憶、悲観的記憶、不安を惹起する記憶等は客観性の低下の為忘れ去ることが困難である)、このことによりほぼ一定量であるメモリーの殆どを占拠することとなって、新しい記憶を残すことが困難となることがある。
これと一見逆のパターンと考えられるのがサヴァン症候群であるとも考えられるのではないか。
但し、このサヴァン症候群は二次機能や実行機能等の他の機能の重い障害を補填する為にこの機能に特化して発達した(或いは出生時~幼少時には容量の多いワーキングメモリーが退化しなかった)とも考えられる。
2014年5月3日
統合失調症の認知機能障害
統合失調症の認知機能障害
情報発生源のモニタリング
情報発生源の記憶もワーキングメモリーに付随して記憶されると言われる。
統合失調症はこの発生源が曖昧となると考えられている。
例えば自他の区別の困難さ、幻聴のような聴覚表象と言語表象との混同などであるが、この混同はワーキングメモリーにまず最初の保存された際に起こる場合もあるが、長期保存から取り出す際に加工されたりすることが考えられ、実行機能障害との関係も否定できない。
2014年5月11日
統合失調症の認知機能障害
統合失調症の認知機能障害
②実行機能障害
実行機能とは、所謂、何かを実行する為の能力である。
これには、
1)様々な状況に応じてその状況を認知、理解、把握。(当然に具体的事象や感情、抽象的事象も含む)
2)その状況に対する対処法を提示し、結果を予想・比して、適応する行動を選択。
3)適応的行動を実行。
4)その結果を判断、フィードバックする。
という一連の複雑な過程をいう。
この為、様々な能力が複雑な相互関係を持っておりこれだけを単独の能力として論じるにはかなり曖昧である。
③ワーキングメモリーと実行機能の関係
ワーキングメモリーと実行機能との関係は、完全に別のものか一つのものかという議論がある。
実行機能が障害され様々な、問題や情報処理に渋滞を生じた場合、例えば深刻で不安な事象が多く頭内を占拠すれば、今、ここで起こっている事象に集中して可能な限り客観的に対象を一次記憶することは困難となることは容易に予想される。
従って私見としては、ワーキングメモリーと実行機能はその境界を厳密に分けて考えることはかなり困難と思う。