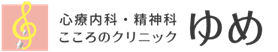日記
2014年5月18日
統合失調症の認知機能障害
統合失調症の認知機能障害
統合失調症の実行機能障害と症状との関係
一口に実行機能と言っても様々で多岐にわたる機能により成立しているが、一連の(様々な状況に応じてその状況を認知、理解、把握→対処法を提示→結果を予想・比較→適応する行動を選択→適応的行動を実行→その結果を判断、フィードバックする。)の行動は全ての過程で障害される可能性がある。
これらの過程はどの過程で障害されても、直接的に又間接的に大きな問題となる。
ストレス下では、基本的には悲観的、被害的等の陰性感情に支配され陰性方向の理解、認知、対処、行動となり易いが、実行機能の障害があると客観的な方向に修正することが出来ない。この誤った認知、実行機能障害が何度か繰り返されると陰性の悪循環に入り、これらは被害妄想、幻聴、幻視を導く可能性がある。
2014年5月25日
統合失調症の認知機能障害
統合失調症の認知機能障害
但し、重要なことは悪循環を来すには前提となる陰性感情が大きなウェイトを占めることである。
つまり、感情と認知はある程度は不可分であり感情をコントロールすることは抜本的ではないものの統合失調症の認知機能や実行機能をある程度は改善させ得る可能性を示唆する。
陰性症状は認知、実行機能の悪化→陰性感情の悪化→認知、実行機能の悪化の悪循環のサーキットとして捉えることが出来る。
この陰性症状に関しても感情のコントロールが非常に重要であり、又、認知、実行機能を障害された認知に対して直接的に認知療法を行ったり、障害された実行機能に対して作業療法を行うよりも、感情をコントロールする方向がより効果的と言える。
又、抗精神病薬も必要であるが抗精神病薬の鎮静効果が統合失調症の認知機能を障害するのは一つはその抗躁効果によるものとも言える。
2014年6月1日
統合失調症の認知機能障害
統合失調症の認知機能障害
統合失調患者に於ける認知機能、実行機能障害をベースに陰性感情が幻覚、幻視、陰性症状を引き起こす可能性を説明したが、逆に陽性感情が起こればどうなるのか。
認知、実行機能の障害された統合失調患者には躁状態の悪化が加わればやはり、容易に客観性の欠如により誇大妄想の悪化や思考のまとまりのなさにより観念奔逸を悪化させる。
又、病識の欠如が更に加速し、多動、多弁等の躁症状の自制が効かず、悪化を加速させることになる。
つまり、認知、実行機能障害は感情によって起こる歪を更に拡大、悪循環化させると言える。