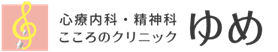日記
2014年6月29日
統合失調症の注意障害
統合失調症の注意障害と自明性の喪失
焦点化や持続的情報処理が障害されることにより、情報処理の遅延や不完全な処理が起こる。
不完全な処理はその背後にある感情に修飾され、悲観的、被害的な結論へと導かれる可能性を示唆する。
又、その処理が不完全で一定、一様でない為に、何度同じ事象、刺激を受けても新しいもののように錯覚することがある。
言い換えれば、その刺激に対する慣れやパターン化が困難であることを意味する。
このパターン化は客観性であり、間主観性であり、これを欠落することは、とりも直さず自明性の喪失を示唆する。
自分自身とは、この世界とはという根幹的命題を失うことにもなる。
2014年7月8日
統合失調症の情報処理過程
統合失調症の情報処理過程でやはり大きな影響力を持ち得るのは、背後にある感情である。
抗精神病薬は感情的に陰性に働くことが多くあり、この場合には情報処理過程を阻害することが考えられる。
又、躁状態の場合にもその陽性の感情に情報処理過程が修飾される可能性を示唆する。
つまり、ある一定以上の躁状態に於いても客観性を失うことが予見できる。
又、統合失調症に於いても、情報処理障害の重症度は感情障害の程度によっても左右され得ると考えられる。
又、一旦、情報処理過程が強く障害され、重度の自明性の障害が持続的に起こってしまうと、その客観性、間主観性を大きく損ない、不可逆的なものになり得る。
2014年7月13日
統合失調症と会話の障害(吃音、呂律が回らない)
統合失調症に於ける会話の障害(吃音、呂律が回らない)はその認知機能障害より説明できる。
①ワーキングメモリーの低下(不安を惹起する記憶等は客観性の低下の為忘れ去ることが困難である)。
このことによりほぼ一定量であるメモリーの殆どを占拠することとなって、新しい記憶を残すことが困難となることがある。
これは他人から話しかけられた際に相手の話を記憶出来ない、自分が話したことを記憶できないことを示唆する。
相手の質問に答えずに自分勝手な話をしたり、自分の話の内容が一貫性を失うこととなるのである。
②二次記憶(陳述記憶、エピソード記憶、手続き記憶)の障害。
通常使用している言葉(ひらがな、カタカナ、簡単な漢字)が出てこない、呂律が回らず吃音となり得る。又、普段に簡単に出来ていた会話が出来なくなる。