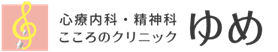日記
2014年7月20日
統合失調症と会話の障害(吃音、呂律が回らない)
統合失調症と会話の障害(吃音、呂律が回らない)
③実行機能障害
1)様々な状況に応じてその状況を認知、理解、把握すること(当然に具体的事象や感情、抽象的事象も含む)。
2)その状況に対する対処法を提示し、結果を予想・比して、適応する行動を選択。
3)適応的行動を実行。
4)その結果を判断、フィードバックする。
という一連の複雑な過程である実行機能障害である。
実行機能が障害されると、何を話して良いか分からなくなる。
判断力、決断力が低下し、場当たり的な的外れな、その場にそぐわない、現実感の無い会話となる。
又、一連の実行機能が停止すれば会話が止まる(思考途絶)こともあり得る。
円滑に言葉を並べて離せなくなればロゴクロヌス(語間代)、パリラリア(反復言語)も起こり得る。これは言語性チックとの関連性も否定できない。
2014年7月27日
統合失調症と会話の障害(吃音、呂律が回らない)
統合失調症と会話の障害(吃音、呂律が回らない)
④注意集中、注意の保持の障害
注意集中・保持が障害されると刺激に対する慣れやパターン化が困難であることを意味する。
このパターン化は客観性であり、間主観性であり、これを欠落することは、とりも直さず自明性の喪失を示唆する。
客観性の歪が生じることにより、過度に被害的、悲観的な会話となることは言うまでもない。
2014年7月27日
新型鬱病に対するアンチテーゼ
新型鬱病に対するアンチテーゼ
新型鬱病の診断基準
気分反応性(好ましいことがあると、気分がよくなる)である。
以下の症状のうち2つ(またはそれ以上)
①著しい体重増加または食欲の増加
②過眠(いくら寝ても眠い)
③鉛様のマヒ(手や足に鉛がつまったように重い感覚)や、激しい疲労感
④批判に対して過敏になり、ひきこもり(気分障害のエピソードの間だけに限定されるものではない)、いちじるしい社会的または職業的障害を引き起こしている。(拒絶過敏症)
同一のエピソードの間にメランコリー型の特徴をともなうもの、または緊張病性の特徴をともなうものの診断基準を満たさない。