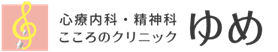日記
2013年6月16日
解離性障害
構造的解離理論
①大きな心理的ストレスを受けると、日常生活に適応的で外傷記憶に退避的である正常的人格部分と情動的人格部分に分裂する。
②ストレスが持続、重度化すると、この情動的人格部分は細分化、精巧化し終には自律化する。
③人格部分は他の人格部分に対して恐怖を覚え、特に正常的人格部分は情動的人格部分に回避的であることより、更に人格部分同志が収束し難い悪循環に陥ってしまう。
④人格の分裂によって、体験は自分の所有物である(個人化)という信念が希薄と成り、現実の世界に於いて、現実適応することが困難となる。
⑤双極性障害、及び統合失調症等の客観性の歪を生じる疾患は、解離性障害と鑑別されなければならないが、非個人化、非現実化を起こしやすく、解離性障害を合併し易いとも言える。
2013年6月21日
鬱病委員会
H25年6月14日、鬱病委員会が行われ
①紹介状の書式;
1)複写でなく一枚で。
2)症状の頻度は問わない。
3)躁状態の鑑別は煩雑となるために行わない。
②勉強会はテキストを使用して、古賀先生と私が講演することになりました。
③精神科・心療内科以外の科の先生に対して、アンケートをお願いすることとなりました。
アンケートの試作案を作成しました。
謹啓 長梅雨の候となりました。先生方におかれましては、ますますご繁盛のこととお喜び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
自殺患者は約3万人前後と危機的状況にあります。
特に、我が国における若い世代の自殺は深刻な状況にあります。年代別の死因順位を見ると、15~39歳の各年代の死因の第1位は自殺となっており、男女別に見ると、男性では20~44歳という、若手社会人として社会を牽引する世代において死因順位の第1位が自殺となっており、女性では15~34歳のさらに若い世代で死因の第1位が自殺となっております。
また、厚生労働省が施行する医療機関に対する患者調査では、平成8年に43万人であった鬱病等の気分障害の患者数は、平成20年には104万人と12年間で2.4倍に増加しております。
鬱病の半数の患者様は医療機関を受診せず、4割の患者様は内科、産婦人科、耳鼻科、整形外科等を受診。精神科・心療内科を受診される患者様は僅か1割です。特に内科を受診される患者の10~20%は鬱病(軽度の鬱病も入れると)の患者といわれておりまして、自殺の多くの原因と思われる鬱病対策に先生方にご助力をお願い申し上げることが不可欠な状況です。
鬱病委員会では先生方と鬱病対策において、緊密な関係を構築し、自殺者数を減少させるべく努力する所存であります。
先ずは先生方のご意見をお聞きしたく、アンケートをお願い申し上げることとなりました。
ご多忙中と思いますが宜しくお願い申し上げます。
以下の質問に○をつけて下さい。
Ⅰ鬱病患者を診察している(①10人未満②10人~19人②20人以上)
Ⅱ鬱病患者を治療しているが、2ヶ月以上経過しても改善傾向に無い患者がいる(①はい②いいえ)
Ⅲ自殺しそうな患者を治療している(①はい②いいえ)
Ⅳ専門機関に紹介しようとするが、患者様が拒否している(①はい②いいえ)
Ⅴ鬱病かもしれないが特に治療をしていない(①10人未満②10人~19人②20人以上)
Ⅵ鬱病かも知れないが、診断が困難であり治療法に困る患者様がいる(①はい②いいえ)
Ⅶ薬(抗鬱薬、安定剤、眠剤)の使い方で困っている(①はい②いいえ)
Ⅷ鬱病の講演会、勉強会があれば出席したい(①はい②いいえ)
Ⅸ鬱病等の精神疾患で困った症例を気軽に相談できる勉強会があれば参加したい(①はい②いいえ)
Ⅹ鬱病委員会に対して、ご希望、ご要望をお願い申し上げます。
先生方の使用されたことのある向精神病薬に○をつけて下さい。
【抗鬱薬】
三環系抗鬱薬
①塩酸クロミプラミン(アナフラニール)
②塩酸イミプラミン(トフラニール、イミドール他)
③塩酸ノルトリプチリン(ノリトレン)
④塩酸アミトリプチリン(トリプタノール他)
⑤塩酸トリミプラミン(スルモンチール)
⑥アモキサピン(アモキサン)
⑦塩酸ロフェプラミン(アンプリット)
⑧塩酸ドスレピン(プロチアデン)
四環系抗うつ薬
⑨塩酸マプロチリン(ルジオミール)
⑩塩酸ミアンセリン(テトラミド)
⑪マレイン酸セチプチリン(テシプール)
その他の第二世代抗うつ薬
⑫塩酸トラゾドン(レスリン、デジレル他)
⑬スルピリド(ドグマチール、アビリット、ミラドール他)
SSRI
⑭マレイン酸フルボキサミン(デプロメール、ルボックス)
⑮塩酸パロキセチン(パキシル)
⑯塩酸セルトラリン(ジェイゾロフト)
⑰蓚酸エスシタロプラム(レクサプロ)
SNRI
⑱塩酸ミルナシプラン(トレドミン)
⑲塩酸ヂュロキセチン(サインバルタ)
NASSA
⑳ミルタザピン(レメロン、リフレックス)
アンケートへのご協力誠に有り難うございました。
今後ともなにとぞよろしくご指導のほどお願い申し上げます。
謹白 鬱病かかりつけ委員会
2013年6月30日
発達障害
発達とADHD
①乳児期;過剰な活動は移動能力の高まる3~6か月と言われており、これを超えて過活動が持続すれば、ADHDの可能性が高まると言われる。
②幼稚園;衝動性、注意集中困難があり、規制内の活動が難しく、ルールが守れないし、理解していない。但し、7歳頃までに改善する児童が多いため、これだけではADHDとの診断は困難である。
③学童期;話を集中して聞けない為、学習に障害が生じ、情動をコントロール出来ない為、子供同志の関係、親子関係を悪化させる。
④青年期;衝動性や多動性は改善傾向となるものの、客観的自己評価が乏しく、場の雰囲気が理解できず信頼関係を上手く構築出来ない。
⑤成人;自分の衝動性、不注意、多動の特徴を自覚し、修正する技術を習得してゆくが、不完全で仕事、人間関係に支障を来し安定した、仕事、家族関係を構成できないことが多い。
衝動買い、順序だった行動や計画性に欠け、時間の感覚がないことがあると言われている。