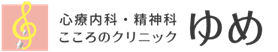日記
2013年7月28日
第3回鬱病かかりつけ委員会
糟屋医師会鬱病かかりつけ委員会(H25年8月予定)
①鬱状態の診断、重傷度診断にSDSを活用
1)情報提供書はDSM-Ⅳ対応で、あるorなしのものに。
2)SDSは月1回チェック。
3)SDSカットオフポイント40点。
②かかりつけ医から専門医に紹介するタイミング(久留米大学)
1)継続する不眠に対して睡眠薬を2週間以上投与しても症状が増悪?する場合
総睡眠時間が5時間を確保できない場合?
2)診断に迷った場合
3)脳の器質的な障害(脳梗塞、パーキンソン症候群など)が疑われる場合
4)第一選択薬の抗鬱薬で効果が認められない場合(4週間~8週間)
★SSRI,SNRIのみの推奨。
★睡眠薬以外のベンゾジアゼピン系の使用に関しては推奨しない。
★眠剤の中でもベゲタミン等のバルビツレートは推奨しない。
★向精神病薬投与一回分の限界(期間)は、中等度以上の鬱病に対しては1~2週間で、重度以上では1週間で。
★効果があるとは、例えばSDS50点以上の患者様に於いて、1ヶ月~2ヶで10点以上改善。
★SDS40点台が長期、例えば6ヶ月以上持続する場合は一度専門医に紹介。
★賦活症候群、QT延長症候群等の副作用の情報が必要、主な薬物の添付文書を薬品会社より配布、副作用を説明してもらう。
5)重症の鬱病(幻覚、妄想を認める)の場合、専門医に紹介。
6)自殺の危険性がある場合
自殺可能性をどのように評価
→根本的には困難であるが、SDS19番目の項目(自分が死んだ方が、他の人が楽に暮らせると思う)で、ないかたまに、時々、しばしば、いつものうち時々以上をカットオフポイントとして危険性ありと評価し専門医に相談。
7)アルコール依存が疑われる場合専門医に紹介。
8)入院が必要だと考えられる場合(家庭や環境の調整が困難)、専門医に紹介。
9)躁症状が出現したことがある場合、専門医に紹介。(初診時に躁状態の既往を聞く必要あり)
③診療情報提供書
一枚のもので、躁状態をはずしたものに(○を付けるのみ)
④かかりつけ医稼動のフィードバック
→紹介された専門医が保健所に報告(久留米のかかりつけ医―精神科医連携報告書を流用?FAXを保健所へ)
⑤後の勉強会は取り敢えず、古賀先生と人見で鬱病アプローチ研修等を使用をして行う。他に講演会、症例検討会を行うか。(実際には一般医の参加者は極めて少ない)
⑥一番の問題点は、他科の先生方に如何にして興味を持ってもらうか。また、如何にして患者さんに不眠や難治性の身体症状が鬱状態によるものの可能性が大きい事を知っていただくか。
1)欝状態を疑うポスター(欝状態で不眠、倦怠感等の身体症状が起こり易く、直りにくいこと、抑鬱気分が無くても身体症状だけの鬱病、仮面鬱病が多いこと、鬱病が心配な方は院内で心理テストを簡単に受けることが出来ること)を院内に掲示して頂く?
2)内容の広告を出す。インターネット、新聞?雑誌?(コストとの関係?)
⑦一般医に対するアンケート(別紙参照)
2013年8月4日
自我意識障害
自我意識障害は統合失調症の症状です。
1.能動性自我意識の障害:自我の能動性が障害されると、離人体験、作為体験、強迫体験などが起こると言われています。
a. 離人体験(離人症):自己および外界について、生き生きとした現実感がなくなる状態です。
外界が現実のものとして感じられず、自分の行動、感情に現実感がなくなる. すべての精神活動が自分がしている、自分のものであるという意識がうすれ、自己能動感がなくなり、同時に 自己所属感が減弱します。なにか別世界を見ているように感じます。これを疎隔体験という。
b. 作為(させられ)体験(被影響体験):自己が自己以外のものから影響され、左右されると感じる体験で、精神活動の自己所属感が消失 して、第三者にあやつられると意識する。作為体験が思考面に現れたのが作為思考であり、考想奪取、考想吹入、考想伝播、考想察知、考想干渉などがある。
c. 強迫体験:強迫体験とは、ある観念や行為が自己の意志に反して起こってきて、どうしても頭から離れず、その観念や行為が不合理なものとわかっていながら取り除くことができない状態をいう。強迫体験は強迫観念と強迫行為 に分けられる。
2.単一性自我意識の障害:自我の単一性が障害されると、自分以外にもう人の自分がいるという体験が生ずる。これを二重身といいます。
3.同一性自我意識の障害:自我の同一性が障害されると、過去と現在の自分が別人となる。同一人に時間的経過とともに2つの自我が交代して現われるのを交代意識、2つの異なった人格が交代して現われるのを交代人格または 二重人格という。
4.限界性自我意識の障害:自我の限界性が障害されると、自分と他人との区別がつかなくなり、自己を他人や外界の事物と同一視する。神や絶対者と一体化したと感ずる恍惚などが相当する。
2013年8月11日
接触障害と躁鬱病
接触障害と躁鬱病
躁鬱病に於ける過食の起こり方。
①躁状態で、食欲が亢進し止まらない場合。
②軽度の鬱状態で、苛々、ムシャクシャして食欲にてこれを代償する場合。
③躁鬱病の鬱状態では、鬱病の症状に加えて統合失調症の諸症状が併せて出現しする為、これに耐えられず自傷行為が起こりやすい。自傷行為の一つのパターンとして過食することがある。(②と共通するところがある)
④統合失調症では自明性、間主観性の喪失、理解力、思考障害を生じ客観性が歪む為にボディイメージが歪む。この為、肥満が怖いという恐怖がコントロール出来ない為に拒食が止まらない。
痩せすぎに対する恐怖より太ることへの抵抗が大きい為、ボディイメージの歪は肥満に対する抵抗に偏る。