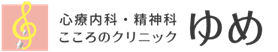日記
2018年8月13日
会話が出来ない
不登校・引きこもりは話が不得意なだけで「人と話したくない」ことはないのに「話したくない」変人と誤解されることが多い
会話をするために
①対人的距離を詰める
1)話せそうな人、話しやすそうな人を見極める
2)友達の友達は友達(対人関係を焦らず広げる。自分を理解、サポートしてくれる人を確保する)
3)自分で話さなくとも、頷いたりして空間を共有する
②会話の切っ掛けの作り方
1)なんといっても挨拶
「おはようございます」、「こんにち」は等で十分。長く話そうとしなくて良い
2)一般的、常識的な会話をする
暫く会ってなければ「元気ですか」「久しぶりでうね」、頻回に会っていれば時候の話題「寒いですね」「すっきりしない天気でね」等
話しかけられて嫌な人はいない
2018年8月19日
会話が出来ない
③話さなくとも聞き手に回る
1)話さなくともある程度の良好な対人関係は作れる
2)相手は話したいことを話せた、自分のことを理解してくれようとしている人が目の前にいることで十分に満足する
3)相手の話したい内容、特異な話題を日頃から探すことが必要
4)自信がない、どうしようもない時には
●相手が褒めて欲しい時には「すごいね」「やったね」、
●相手が慰めてもらい時には「困ったね」「きついね」等一言のみをくり返す
2018年8月26日
会話が出来ない
④共有できる話題を選択する
自分の得意な話題であっても相手の無関心な、或いは不得意で嫌な話題であることもしばしばであることを自覚する
1)ある程度話を長くするためには、自分にも相手にもある程度関心のある話題を選択することが必要である
2)それは、自分との関係がどの様な関係であるかを特定することが必要である
●関係の質的特徴はどうか
何のグループに属する友人なのか、先輩か後輩か、上司か部下か
●関係の深さに関する量的関係はどうか
親友か疎遠な友人か、通常の先生か信頼する師匠か
3)関係の質、深さにより共通の質を敵話題を選択し、深さも選ぶことによって安全に会話が出来る
ただしこの作業は複雑であるが通常は一瞬で、直観的に行うことが多い
自明性の喪失がある疾患(統合失調症、双極性障害等)であると、この作業に支障をきたすことも多いが、パターン化して常にトレーニングすることによって克服は出来る