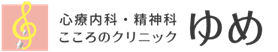人は生まれてより、様々なコミニュケーションによって、獲得した知識が体系化され、直感「当たり前なこと」として把握でき、その上に言語や様々な技術が成りたっているのです。
「自然な自明性」とは、「当たり前なこと」であり、それによって、いつも同じ日常生活や対人関係を、意識せずに送ることが出来るのです。
この「自然な自明性の喪失」によって、理解力が低下したり、気楽さや安心感が無くなる事があるのです。
統合失調症の治療
お薬には第1世代のものから第3世代まで、あり、最近は副作用の少ないもの(第3世代)が主流です。
間主観性
この関わり合いによって、様々な物事、事象が客観性を持つことになるのです。
客観的事実と思われる事象に基づいた主観、直感を「間主観性」といいます。
この間主観性が統合失調症では時に欠落し、客観性を持てなくなることがあるのです。
統合失調症の症状
- 思考障害
- 思考のまとまりのなさや妄想(その内容が置かれている状況から連想し難く、確信を持つ)
- 幻覚(幻聴が多い)
- 自我意識障害(自分の身体、精神をコントロール出来ない、現実感の無い離人感、時間の感覚の低下等) 等)
- 感情の平板化、意志や欲動、自発性の低下
- 喜怒哀楽の喪失、低下
- 認知機能障害
- 判断力、抽象的思考能力、記憶力の低下等
妄想
客観性を失った意味づけ、誤った意味づけを包含した秩序を構築することとなります。この意味づけは繰り返し用いられる度に次第に確固たる信念を獲得してゆき、この誤った意味づけの上に様々な意味づけが関連付けられる為、妄想として発展してゆくことになるのです。
幻覚
統合失調症の方は言葉の意味が曖昧となり、言葉の客観性・普遍性が失われ、その由来さえ不明瞭な状態となることがあります。
窮地に追い込まれた際に、脳に感じる言葉が自分の考えによるものなのか、外部からの情報なのか区別できなくなることがあり(言語表象と聴覚表象の混同)、これによって、幻聴や思考仮声(自分の考えが声として聞こえる)が生ずると思われます。
【1】一般的な記憶の種類
比較的短時間記憶に留められるがやがて忘れられる記憶。 忘れ去ることは日常生活上の一つの適応能力と言えます。
・二次記憶(陳述記憶、エピソード記憶、手続き記憶)
一次記憶が短期の記憶であり、短期のみ必要とされる記憶であることに対して、二次記憶は長期に必要とされ(想起)、情報処理される記憶です。
これは膨大な情報を自分にとっての必要性、特徴を整理して、保存しつつ必要に応じて使用できるようにする機能です。
単語の意味の記憶(陳述記憶)、印象深い出来事の記憶(エピソード記憶)、手続き記憶(一連の動作を覚える記憶)です。
・長期記憶
長期に渡って記憶を保持し、これを活用する能力です。
【2】統合失調症に於ける一次記憶(ワーキングメモリー)障害
根本的には直ぐに消去(忘れ去られる)される記憶ではありますが、統合失調症は一部分ワーキングメモリーの消去が困難となることがあり(被害的記憶、悲観的記憶、不安を惹起する記憶等は客観性の低下の為忘れ去ることが困難である)、このことによりほぼ一定量であるメモリーの殆どを占拠することとなって、新しい記憶を残すことが困難となることがあるのです。
これと一見逆のパターンと考えられるのがサヴァン症候群(記憶力がずば抜けています。)であるとも考えられるのではないでしょうか。
但し、このサヴァン症候群は二次機能や実行機能等の他の機能の重い障害を補填する為にこの機能に特化して発達した(或いは出生時〜幼少時には容量の多いワーキングメモリーが退化しなかった)とも考えられます。
【3】情報発生源のモニタリング
統合失調症はこの発生源が曖昧となると考えられているのです。
例えば自他の区別の困難(自分の考えなのか、他人の考えなのか分かりに難くなる)さ、幻聴のような聴覚表象(外から聞こえてくる記号、イメージ)、と言語表象(自分で考えた記号、イメージ)との混同などです。
この混同はワーキングメモリーにまず最初の保存された際に起こる場合もありますが、長期保存から取り出す際に加工されたりすることも考えられ、後出する実行機能障害との関係も否定は出来ません。
【4】実行機能障害
これには、
様々な状況に応じてその状況を認知、理解、把握(当然に具体的事象や感情、抽象的事象も含む)。
その状況に対する対処法を提示し、結果を予想・比して、適応する行動を選択。
適応的行動を実行。
その結果を判断、フィードバックする。
という一連の複雑な過程を言います。
この為、様々な能力が複雑な相互関係を持っておりこれだけを単独の能力として論じるにはかなり曖昧です。
【5】ワーキングメモリーと実行機能
実行機能が障害され様々な、問題や情報処理に渋滞を生じた場合、例えば深刻で不安な事象が多く頭内を占拠すれば、今、ここで起こっている事象に集中して可能な限り客観的に対象を一次記憶することは困難となることは容易に予想されます。
従って私としましては、ワーキングメモリーと実行機能はその境界を厳密に分けて考えることはかなり困難と思うのです。
【6】実行機能障害と症状
これらの過程はどの過程で障害されても、直接的に又間接的に大きな問題となります。
ストレス下では、基本的には悲観的、被害的等の陰性感情に支配され陰性方向の理解、認知、対処、行動となり易いのですが、実行機能の障害があると客観的な方向に修正することが出来ません。この誤った認知、実行機能障害が何度か繰り返されると陰性の悪循環に入り、これらは被害妄想、幻聴、幻視を導く可能性があるのです。
【7】認知機能障害と感情
一口に実行機能と言っても様々で多岐にわたる機能により成立していますが、一連の(様々な状況に応じてその状況を認知、理解、把握→対処法を提示→結果を予想・比較→適応する行動を選択→適応的行動を実行→その結果を判断、フィードバックする。)の行動は全ての過程で障害される可能性があるのです。
これらの過程はどの過程で障害されても、直接的に又間接的に大きな問題となります。
ストレス下では、基本的には悲観的、被害的等の陰性感情に支配され陰性方向の理解、認知、対処、行動となり易いのですが、実行機能の障害があると客観的な方向に修正することが出来ません。この誤った認知、実行機能障害が何度か繰り返されると陰性の悪循環に入り、これらは被害妄想、幻聴、幻視を導く可能性があるのです。
【8】認知機能障害と双極性障害
統合失調患者に於ける認知機能、実行機能障害をベースに陰性(悲観的過ぎる)の感情が幻覚、幻視、陰性症状を引き起こす可能性を説明しましたが、逆に陽性(ポジティブ過ぎる)の感情が起こればどうなるのでしょうか。
認知、実行機能の障害された統合失調の患者様には躁状態の悪化が加わればやはり、容易に客観性の欠如により誇大妄想の悪化や、思考のまとまりのなさにより観念奔逸(考えが様々な方向に飛びます)を悪化させることが推測されます。
又、病識の欠如が更に加速し、多動、多弁等の躁症状の自制が効かず、悪化を加速させることにもなります。
つまり、感情が上下は認知、実行機能障害の歪を更に拡大、悪循環化させてしまうのです。
【9】注意機能とは
注意の集中は
その事象、刺激の過去の処理が自動的に処理されるようになった場合(車の運転の際の標識等)に起こりやすくなります。つまり、その処理過程に於ける焦点化の維持が円滑に進められることが必要です。
その事象、刺激が有害、恐怖、快楽等のインパクトの強い物である場合にも注意は集中します。
逆に全く事象や刺激が理解、分析出来なければ、焦点を当てることさえ出来ないのです。
【10】選択的注意
通常、様々な事象、刺激の中であるものを選択的に判断するということは、遭遇する全ての事象、刺激をある程度判別、処理、取捨選択しなければならず、云わばマルチタスクの処理が必要なのです。
この処理は総合的な認知機能を必要とします。この過程で、情報処理が遅滞すれば、焦点化は失敗し、必要な情報、刺激を処理出来なくなるのです。
又、過度に悲観的、被害的に処理が行われると、その焦点化ポイントが多くなり、本来、必要で注意を向けるべき選択的注意(運転中に標識を見て判断する)ばかりでなく、持続的処理(例えば車を運転し続けるというような持続的な処理)も障害され、情報処理容量は低下します。この典型例が、思考途絶や強迫性の障害です。
【11】注意の保持(覚性)
能動的に目的(意志)を持ち続け、正確・適応的に且つ、落ち着いて(安定性)処理することが必要です。
これは、全般的で複雑な能力です。
①欲動の低下はこの能動性を、
②間主観性(客観的事実と思われる事象に基づいた主観、直感)の障害は正確性・適応能力を、
③被害妄想、被害関係念慮(妄想まではなくとも被害的な感じが強い)、妄想気分(何か不吉なことが起こりそうで怖い)
等の不安症状は安定性を直接的に障害します。
この能動的・主体的な注意集中・処理能力は社会適応能力とも言え、この障害は人格としてのありようにも大きく修飾してゆくのです。
【12】自明性の喪失、自我意識障害
又、その処理が不完全で一定、一様でない為に、何度同じ事象、刺激を受けても新しいもののように錯覚することがあります。言い換えれば、その刺激に対する慣れやパターン化が困難であることを意味するのです。
このパターン化は客観性であり、間主観性(客観的事実と思われる事象に基づいた主観、直感)であり、これを欠落することは、とりも直さず自明性(空気のように何も考えなくとも自動的に行えたり、生活できる当たり前の事象、法則)の喪失であることを意味します。自我意識障害(時間的・空間的・能動的に自分が自分でない感覚)のように自明性の喪失による「自分自身とは」という命題の喪失は、取りも直さず自分の周囲を占める「この世界とは」という根幹的命題の喪失でもあるのです。
【13】会話の障害
統合失調症に於ける会話の障害(吃音、呂律が回らない)はその認知機能障害より説明できます。
ワーキングメモリーの低下(不安を惹起する記憶等は客観性の低下の為、忘れ去ることが困難です)
このことによりほぼ一定量であるメモリーの殆どを占拠することとなって、新しい記憶を残すことが困難となることがあるのです。これは他人から話しかけられた際に、相手の話を記憶出来ない、自分が話したことを記憶できないことを示唆します。相手の質問に答えずに自分勝手な話をしたり、自分の話の内容が一貫性を失うこととなるのです。
二次記憶(陳述記憶、エピソード記憶、手続き記憶)の障害
通常使用している言葉(ひらがな、カタカナ、簡単な漢字)が出てこない、呂律が回らず吃音となり得ます。又、普段に簡単に出来ていた会話が出来なくなることもあります。
実行機能障害
実行機能が障害されると、何を話してよいか分からなくなります。判断力、決断力が低下し、場当たり的な的外れな、その場にそぐわない、現実感の無い会話となります。又、一連の実行機能が停止すれば会話が止まる(思考途絶)こともあり得る。円滑に言葉を並べて離せなくなればロゴクロヌス(語間代)、パリラリア(反復言語)も起こり得ます。これは言語性チックとの関連性も否定できません。
注意集中、注意の保持の障害
注意集中・保持が障害されると刺激に対する慣れやパターン化が困難であることを意味します。このパターン化は客観性であり、間主観性(客観的事実と思われる事象に基づいた主観、直感)であり、これを欠落することは、とりも直さず自明性の喪失(時間的・空間的・能動的に自分が自分でない感覚)を示唆します。客観性の歪が生じることにより、過度に被害的、悲観的な会話となることは言うまでもありません。