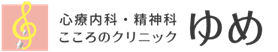不登校と家庭内暴力
様々な原因、要素があり得る。
①本人:言語表現能力が低かったり、自己主張が難しい場合や対人関係を被害的に捉えやすい場合等が考えられるが、これらによって対人関係に支障を生じてしまって孤立。ストレスを外に向かって発散出来なくなる。
②環境:家庭内で本来無条件に受け入れてくれるはずの両親に指示的・共感的対応がない場合や学校での不安定な対人関係や学業の低下による自信の無さ等は感情のコントロールを困難にする。
③不登校児は自信なく閉居しており、ストレスの耐性は低い。
ストレスの発散の手段も少なく唯一の発散は家庭である。
この為、無条件にストレスを受け止めてくれるように家族に強制する。
勿論これは教育上限度がある。両親も節度を持って対応せざるを得ない為、不登校児はストレスを十分には発散出来ない。
①本人:言語表現能力が低かったり、自己主張が難しい場合や対人関係を被害的に捉えやすい場合等が考えられるが、これらによって対人関係に支障を生じてしまって孤立。ストレスを外に向かって発散出来なくなる。
②環境:家庭内で本来無条件に受け入れてくれるはずの両親に指示的・共感的対応がない場合や学校での不安定な対人関係や学業の低下による自信の無さ等は感情のコントロールを困難にする。
③不登校児は自信なく閉居しており、ストレスの耐性は低い。
ストレスの発散の手段も少なく唯一の発散は家庭である。
この為、無条件にストレスを受け止めてくれるように家族に強制する。
勿論これは教育上限度がある。両親も節度を持って対応せざるを得ない為、不登校児はストレスを十分には発散出来ない。
不登校と鬱状態
気分が低下した(落ち込んだ)状態と、病的なうつ状態との違いは、悪循環に入っている(治りにくい)か否かにある。
➀精神的悪循環サーキット
②精神症状⇔身体症状悪循環サーキット
➀精神的悪循環サーキット
②精神症状⇔身体症状悪循環サーキット
【1】精神的悪化のサーキット
①契機が何かにも左右されるが、結果として起こってしまった「不登校」は周囲の目が自分に否定的に感じられるようになる。
①-1最も気になるものは学友の目であり、自分の評価を「怠けている・学校をサボっている」「やる気がない」というように劣等感を強く感じてしまう。
①-2教師からの目が気になるようになる。教師は学校で自分を「評価」し「指導」を行う存在である。不登校は周囲の学友と比較して「劣っている」「ダメな生徒である」と評価され、努力するように厳しく「指導される」のではないかと恐れる。
①-3家族からも、最も気持ちを理解してくれるはずの存在であるはずが、「怠けている」「根性がないだけ」「努力が足りないだけ」等のように自分を理解してくれないだろうと考える。
①-4登校して勉強するチャンスを失い、家でも集中力・意欲が低下する為勉強が遅れるが、この遅れは「厳然とした遅れ」である。「遅れ」はどう考え直しても否定できない事実であって、自己否定的思考は確実に強化される。」
②不登校が持続すればするほど、周囲に対する否定的思考は孤独感を呼ぶだけでなく、周囲が考えているとうりに「自分はダメで努力出来ない」存在であると確信してしまう。つまり自己否定的思考を強化する自己否定的悪循環サーキットに入る。
①-1最も気になるものは学友の目であり、自分の評価を「怠けている・学校をサボっている」「やる気がない」というように劣等感を強く感じてしまう。
①-2教師からの目が気になるようになる。教師は学校で自分を「評価」し「指導」を行う存在である。不登校は周囲の学友と比較して「劣っている」「ダメな生徒である」と評価され、努力するように厳しく「指導される」のではないかと恐れる。
①-3家族からも、最も気持ちを理解してくれるはずの存在であるはずが、「怠けている」「根性がないだけ」「努力が足りないだけ」等のように自分を理解してくれないだろうと考える。
①-4登校して勉強するチャンスを失い、家でも集中力・意欲が低下する為勉強が遅れるが、この遅れは「厳然とした遅れ」である。「遅れ」はどう考え直しても否定できない事実であって、自己否定的思考は確実に強化される。」
②不登校が持続すればするほど、周囲に対する否定的思考は孤独感を呼ぶだけでなく、周囲が考えているとうりに「自分はダメで努力出来ない」存在であると確信してしまう。つまり自己否定的思考を強化する自己否定的悪循環サーキットに入る。
【2】精神的悪循環サーキット
③人の目が気になることが全般化し、孤立することになり解決すべき問題や、不安を相談できる環境やチャンスを自ら減らしてしまう。
④誰にも相談できず精神的に追い詰められて不安や悲観的思考が強化されて問題を解決すべき方向性や方法を客観的に捉えられなくなり絶望感に陥る。
⑤周囲の目が過度に気になることによって、外出の意欲が低下し次第に外出が怖くなり、不登校というだけでなく引きこもりの状況になってしまう。
⑥引きこもりとなってしまえば、当然に気分転換も出来難くなるだけでなく、一日中悲観的思考に埋没してしまい、思考を修正することも出来ず、何をすればよいのか、何をすべきか分からず途方に暮れる毎日となってしまう。
⑦こうなると前に述べた「精神的悪循環サーキット」の認知の歪を修正出来なくなり「難治性鬱状態」ともなってしまうのである。
⑧状況に対する悲観的過大評価「うつ状態は治らない、更に悪くなる一方だ。」「光が見えない、どうしてよいのか分からない。」という破滅的精神状態に陥る。
④誰にも相談できず精神的に追い詰められて不安や悲観的思考が強化されて問題を解決すべき方向性や方法を客観的に捉えられなくなり絶望感に陥る。
⑤周囲の目が過度に気になることによって、外出の意欲が低下し次第に外出が怖くなり、不登校というだけでなく引きこもりの状況になってしまう。
⑥引きこもりとなってしまえば、当然に気分転換も出来難くなるだけでなく、一日中悲観的思考に埋没してしまい、思考を修正することも出来ず、何をすればよいのか、何をすべきか分からず途方に暮れる毎日となってしまう。
⑦こうなると前に述べた「精神的悪循環サーキット」の認知の歪を修正出来なくなり「難治性鬱状態」ともなってしまうのである。
⑧状況に対する悲観的過大評価「うつ状態は治らない、更に悪くなる一方だ。」「光が見えない、どうしてよいのか分からない。」という破滅的精神状態に陥る。
「もう全ては終わりだ、自分は大きく周囲に迷惑をかけてきた」(拡大解釈)「家族や周囲も不幸になる」(過度の一般化」。
こういった自己対処能力低下(認知の歪、狭小化)がうつ状態を出口のない泥沼に誘導(悲観的思考が更なる悲観的思考を誘導する)する。
「どうにかこの悪い状態を脱したい、何とかしよう。」⇔「体も頭も動かない、もうどうしようもない。」肯定的思考と悲観的思考を絶え間なく、出口なく、四六時中揺れ動く。
【2】精神的悪循環サーキット、難治性鬱状態
克服出来ない大きなストレス(経済的ストレスや難治性の身体疾患、改善困難な対人関係等)存在する場合が多いが、個人のストレス自体に対する感受性にも問題がある場合が多い事も事実である。
ストレス自体の感受性が置かれた状況に比較して高くなっている場合があり、不登校や引きこもりもこの場合が多い。
状況を客観視出来ず不当に不安視する場合は、客観性の歪みを生じる精神疾患を疑わなくてはならない。
又、ストレスの感受性の問題だけでなく、その解決方法にも客観性の歪みを生じる精神疾患の場合大きな支障を生じる。
「治るために何時、何を、どういった優先順位でなすべきなのか」を考えることが出来ずに途方に暮れてしまう。こういった解決方法を見失い易いことも不登校や引きこもりに多く見受けられる。
状況悪化が客観的思考を障害し、結果としてストレスの過大評価、解決方法の同定が不能となり鬱状態や不登校、引きこもりを悪化させる悪循環に陥る。
ストレス自体の感受性が置かれた状況に比較して高くなっている場合があり、不登校や引きこもりもこの場合が多い。
状況を客観視出来ず不当に不安視する場合は、客観性の歪みを生じる精神疾患を疑わなくてはならない。
又、ストレスの感受性の問題だけでなく、その解決方法にも客観性の歪みを生じる精神疾患の場合大きな支障を生じる。
「治るために何時、何を、どういった優先順位でなすべきなのか」を考えることが出来ずに途方に暮れてしまう。こういった解決方法を見失い易いことも不登校や引きこもりに多く見受けられる。
状況悪化が客観的思考を障害し、結果としてストレスの過大評価、解決方法の同定が不能となり鬱状態や不登校、引きこもりを悪化させる悪循環に陥る。
難治性鬱病とは
難治性うつ病の定義としては、「少なく とも2種類の抗うつ薬を十分量 (imipramine 相当で日に 150 mg) 十分 な期間 (4~6週間) 用いても反応がみ られない」難治性鬱病には、様々な原因、病状が考えられる。
克服出来ない大きなストレス(経済的ストレスや難治性の身体疾患、改善困難な対人関係等)存在する場合が多いが、ストレス自体の感受性にも問題がある場合が多い事も事実である。
難治性の「鬱病」という定義は果たして適切か否か様々な精神疾患が悪化すれば鬱状態になり得る。
又、単に鬱状態だけでなく他の精神疾患を合併するからこそ難治性となることが多く、難治性「鬱状態」と考えた方が状況を的確に説明出来得る。
克服出来ない大きなストレス(経済的ストレスや難治性の身体疾患、改善困難な対人関係等)存在する場合が多いが、ストレス自体の感受性にも問題がある場合が多い事も事実である。
難治性の「鬱病」という定義は果たして適切か否か様々な精神疾患が悪化すれば鬱状態になり得る。
又、単に鬱状態だけでなく他の精神疾患を合併するからこそ難治性となることが多く、難治性「鬱状態」と考えた方が状況を的確に説明出来得る。
【3】精神症状⇔身体症状悪循環サーキット
①不登校となって周囲の目が気になり、悲観的思考、被害的思考、不安感が強くなることによって緊張感が一日を通して亢進することになり、前に述べた倦怠感、不眠、腹痛、下痢、嘔吐等の身体症状を引き起こす。
②倦怠感は登校、コミニュケーション、友人と遊ぶこと等重要な日常生活に対する意欲、集中力を低下させる。引いては問題を整理、解決する意欲をも奪って登校だけでなく将来に対して、或いは今ここで生きることに対する絶望感を引き起こす。
③明日、登校しなければならないという不安、登校した時の友人や教師が自分を軽蔑するであろうという不安、明日登校しなければ更に自分の人生は破滅に向かうであろうという不安によって緊張感は更新して不眠となる。
不眠は前述の倦怠感を引き起こすだけでなく昼夜逆転につながり(更に翌日の不眠へとつながることとなり)、絶望感を引き起こす。
④倦怠感、腹痛、下痢、嘔吐等は登校の意欲を阻害させ、また、本人に不登校の口実、免罪符を与える。
②倦怠感は登校、コミニュケーション、友人と遊ぶこと等重要な日常生活に対する意欲、集中力を低下させる。引いては問題を整理、解決する意欲をも奪って登校だけでなく将来に対して、或いは今ここで生きることに対する絶望感を引き起こす。
③明日、登校しなければならないという不安、登校した時の友人や教師が自分を軽蔑するであろうという不安、明日登校しなければ更に自分の人生は破滅に向かうであろうという不安によって緊張感は更新して不眠となる。
不眠は前述の倦怠感を引き起こすだけでなく昼夜逆転につながり(更に翌日の不眠へとつながることとなり)、絶望感を引き起こす。
④倦怠感、腹痛、下痢、嘔吐等は登校の意欲を阻害させ、また、本人に不登校の口実、免罪符を与える。
【3】不登校の予後
不登校は、主に精神障害の存続、悪化に関連している。予後良好な要因には、
①症状の急性発症
②発症時の年齢が若い
③学校に通っていない時間が短い
④早期診断と治療
⑤精神医学的罹患率の低下
⑥不登校の頻度が少ないことが挙げられる。
逆に、不登校が慢性化するリスクは、援助が迅速に行われず保護的な要因が欠けている場合に増加する。
①症状の急性発症
②発症時の年齢が若い
③学校に通っていない時間が短い
④早期診断と治療
⑤精神医学的罹患率の低下
⑥不登校の頻度が少ないことが挙げられる。
逆に、不登校が慢性化するリスクは、援助が迅速に行われず保護的な要因が欠けている場合に増加する。
【3】不登校の予後 難治性鬱病等の精神疾患と不登校
①不登校児の親は、対照よりも不安と鬱病スコアが高かった。 不登校、両親による体罰、親または他の親族における精神障害の病歴の重要性が認められた。
Parental psychological symptoms and familial risk factors of children and adolescents who exhibit school refusal .Bahili K et al (East Asian Archieves of psychiatry 2011 Dec;21(4):164-9.)
②長期間にわたるフォローアップ研究では、不登校児の少なくとも3分の1は、後の人生で精神的な問題を呈していることが示されている。
School Avoidance From the Point of View of Child and Adolescent Psychiatry Symptomatology, Development, Course, and Treatment. Martin Knollmann (Dtsches Arzte Blatt int. 2010 Jan; 107(4): 43–49.)
Parental psychological symptoms and familial risk factors of children and adolescents who exhibit school refusal .Bahili K et al (East Asian Archieves of psychiatry 2011 Dec;21(4):164-9.)
②長期間にわたるフォローアップ研究では、不登校児の少なくとも3分の1は、後の人生で精神的な問題を呈していることが示されている。
School Avoidance From the Point of View of Child and Adolescent Psychiatry Symptomatology, Development, Course, and Treatment. Martin Knollmann (Dtsches Arzte Blatt int. 2010 Jan; 107(4): 43–49.)
【4】不登校への介入、治療の可能性
①その問題点に対して過剰に不安に、深刻に捉えていないか
②問題点と問題点が関連して、袋小路になっていないか
③問題点に対して強迫観念、l強迫行為がないか
④問題点を階層化捉してえる
⑤解決するべき問題点の中で簡単にアプローチできるものを特定する
⑥発達そのものの遅延、他の精神疾患はないかを検討する囲についていけない(集団に帰属できない)ことに介入する
1)ステップルーム、不登校専用の学級を利用する
2)学校以外のグループ(塾、バイト、ボランティア等)を利用する
3)宿題、予習等することが出来なくても。怒られない状況、先生から当てられない状況、つまり恥をかかされないように学校に配慮してもらう
4)ステップルームや保健室より先生と一緒に教室に誘導してもらう
5)教室に居る時間を徐々に延長する
6)部活等の勉学以外の学校行事で親しみやすいものから慣れてゆく
③社会的に認められ、受け入れられる年齢相応の自我ではないことに介入する
1)規則正しい生活や外出、散歩等を行い、自分で自分の生活、行動を自由にコントロール出来るようにして日常生活における自信を養う
2)状況、体調にあった目標、日課を設定し、達成してゆくことで自信を養う
3)学習に関しては、学校に行かなくともできるはずなので、両親、家族に手伝ってもらいながら確実に前に進めることが必要
部屋に閉じこもらずに居間で勉強する
学習が前に進んでいることが自信をつける大きな要因でもある
4)家事を手伝うことも重要である、家族にとっても本人を褒めることが出来る切っ掛けをつくることになる
④周囲より低く見られ、軽蔑される自我に違いないと思い込むことに介入
1)不当に自分の能力、資質、人格を低く認知していることを共感的に説明
2)被害的になり過ぎている場合、薬物療法、精神療法等を勧める
3)自信を持てるように運動、塾や家庭教師による学力アップを図ってみる
4)空しい生活を送らないように規則正しい生活を送る
5)家事をさせ、その対価として賞賛したり小遣いを与える。
6)先ずは自信のなさ、将来への不安に対してしっかりと耳を傾ける。
⑤学校(年齢相応で適応すべき社会)には怖くて行けない⇔自己評価の過剰な低下という悪循環に迷入することに介入
1)学校の勉強についていけなくとも、人格的に劣っているわけではないことを強調
2)自己主張と社会性のバランスを様々な時を捉えて話し合い、実践的に行えるように工夫する。
②問題点と問題点が関連して、袋小路になっていないか
③問題点に対して強迫観念、l強迫行為がないか
④問題点を階層化捉してえる
⑤解決するべき問題点の中で簡単にアプローチできるものを特定する
⑥発達そのものの遅延、他の精神疾患はないかを検討する囲についていけない(集団に帰属できない)ことに介入する
1)ステップルーム、不登校専用の学級を利用する
2)学校以外のグループ(塾、バイト、ボランティア等)を利用する
3)宿題、予習等することが出来なくても。怒られない状況、先生から当てられない状況、つまり恥をかかされないように学校に配慮してもらう
4)ステップルームや保健室より先生と一緒に教室に誘導してもらう
5)教室に居る時間を徐々に延長する
6)部活等の勉学以外の学校行事で親しみやすいものから慣れてゆく
③社会的に認められ、受け入れられる年齢相応の自我ではないことに介入する
1)規則正しい生活や外出、散歩等を行い、自分で自分の生活、行動を自由にコントロール出来るようにして日常生活における自信を養う
2)状況、体調にあった目標、日課を設定し、達成してゆくことで自信を養う
3)学習に関しては、学校に行かなくともできるはずなので、両親、家族に手伝ってもらいながら確実に前に進めることが必要
部屋に閉じこもらずに居間で勉強する
学習が前に進んでいることが自信をつける大きな要因でもある
4)家事を手伝うことも重要である、家族にとっても本人を褒めることが出来る切っ掛けをつくることになる
④周囲より低く見られ、軽蔑される自我に違いないと思い込むことに介入
1)不当に自分の能力、資質、人格を低く認知していることを共感的に説明
2)被害的になり過ぎている場合、薬物療法、精神療法等を勧める
3)自信を持てるように運動、塾や家庭教師による学力アップを図ってみる
4)空しい生活を送らないように規則正しい生活を送る
5)家事をさせ、その対価として賞賛したり小遣いを与える。
6)先ずは自信のなさ、将来への不安に対してしっかりと耳を傾ける。
⑤学校(年齢相応で適応すべき社会)には怖くて行けない⇔自己評価の過剰な低下という悪循環に迷入することに介入
1)学校の勉強についていけなくとも、人格的に劣っているわけではないことを強調
2)自己主張と社会性のバランスを様々な時を捉えて話し合い、実践的に行えるように工夫する。
そのほか
躁鬱(そううつ)病について
鬱病について
パニック障害について
統合失調症(自明性の喪失)について
不眠について
社会不安障害について
生理前症候群について
多重人格障害について
強迫性障害について
気分障害について
いじめ対策について
チック症について
摂食障害について
不登校と家庭内暴力
発達障害について