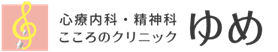摂食障害について
摂食障害 摂食障害の分類
①異食症
乳幼児期の子供が、ゴミや小さなおもちゃ、紙、粘土、石、排泄物など食べ物ではないもの(栄養価のない異物)を選好して食べようとする障害。
成人期以降にも見られることはある。
②反芻性障害
相対的に男児に多い。哺育行動が正常に機能していた期間の後に、少なくとも1ヶ月間にわたって、食物の吐き戻し及び噛み直しの反芻行為が見られる障害。
③回避性・制限性食物摂取障害
『やせ願望・肥満恐怖』といった『ボディイメージの障害及びダイエット欲求』がないにも関わらず、摂食行動を過度に回避したり栄養価を制限したりする障害。
自分自身でも、食べられない原因を言語化・客観視しづらい障害である。
③神経性無食欲症
極端に食欲が低下したり無くなったりする、あるいは著しい摂取カロリーの制限をする摂食障害で、過食と嘔吐(浄化行動)を伴うことが多い。
一般的に『拒食症』と呼ばれることもあるが、『やせ願望・肥満恐怖』に基づく『ボディイメージの障害』が原因としてあることが多い。
④神経性大食症
極端に食欲が増加したり大量の食物摂取行動を制御できなくなったりする、あるいは『非機能的なダイエット行動(過剰な痩せたい欲求)とその失敗』によって過食と嘔吐を繰り返す摂食障害である。
一般的に『過食症』と呼ばれることもあるが、 『やせ願望・肥満恐怖』に基づく『ボディイメージの障害』が原因としてあり、『極端なカロリー制限の反動(リバウンド)』としてストレス解消的な過食行動に陥ってしまうこともある。
⑤むちゃ食い障害
肥満者に多い摂食障害で、過度のダイエットや食事制限をすることはなく、『食欲のコントロール困難』と『食べる量の多さ』が見られる障害。
神経性大食症のように過食後の嘔吐(排出行動)は見られず、過度のダイエットや運動といった『代償行動』も見られないという特徴がある。
気分障害(うつ病)や双極性障害、不安障害とオーバーラップ(重複)することが多く、『体重・体型に対する関心』はあるが具体的に過度なダイエットをすることは殆どないが、過去にダイエットの挫折経験を抱えていることが多い
乳幼児期の子供が、ゴミや小さなおもちゃ、紙、粘土、石、排泄物など食べ物ではないもの(栄養価のない異物)を選好して食べようとする障害。
成人期以降にも見られることはある。
②反芻性障害
相対的に男児に多い。哺育行動が正常に機能していた期間の後に、少なくとも1ヶ月間にわたって、食物の吐き戻し及び噛み直しの反芻行為が見られる障害。
③回避性・制限性食物摂取障害
『やせ願望・肥満恐怖』といった『ボディイメージの障害及びダイエット欲求』がないにも関わらず、摂食行動を過度に回避したり栄養価を制限したりする障害。
自分自身でも、食べられない原因を言語化・客観視しづらい障害である。
③神経性無食欲症
極端に食欲が低下したり無くなったりする、あるいは著しい摂取カロリーの制限をする摂食障害で、過食と嘔吐(浄化行動)を伴うことが多い。
一般的に『拒食症』と呼ばれることもあるが、『やせ願望・肥満恐怖』に基づく『ボディイメージの障害』が原因としてあることが多い。
④神経性大食症
極端に食欲が増加したり大量の食物摂取行動を制御できなくなったりする、あるいは『非機能的なダイエット行動(過剰な痩せたい欲求)とその失敗』によって過食と嘔吐を繰り返す摂食障害である。
一般的に『過食症』と呼ばれることもあるが、 『やせ願望・肥満恐怖』に基づく『ボディイメージの障害』が原因としてあり、『極端なカロリー制限の反動(リバウンド)』としてストレス解消的な過食行動に陥ってしまうこともある。
⑤むちゃ食い障害
肥満者に多い摂食障害で、過度のダイエットや食事制限をすることはなく、『食欲のコントロール困難』と『食べる量の多さ』が見られる障害。
神経性大食症のように過食後の嘔吐(排出行動)は見られず、過度のダイエットや運動といった『代償行動』も見られないという特徴がある。
気分障害(うつ病)や双極性障害、不安障害とオーバーラップ(重複)することが多く、『体重・体型に対する関心』はあるが具体的に過度なダイエットをすることは殆どないが、過去にダイエットの挫折経験を抱えていることが多い
摂食障害の精神病理
現在の定説では親が期待したとうりに子を操作しようとして甘やかしたり、叱ったりする。こういった子供の視線とそぐわない親の態度は子の客観性の発達を阻害すると言われる。
簡単に説明すれば以下の様である。
①子供は自身に内在すべき自己規範が持てなくなり親の顔色見て行動するようになる。
②自分の視点にそぐわない親に対して愛情を感じることは出来ずに、怯えることとなる。
③この親に対する認知パターンは、他の対人関係にも波及することとなる。
子供の視線とそぐわない親の態度は確かに子の客観性の発達を阻害する可能性があるが、これが主たる原因だろうか。
元々、客観性の歪を生じる統合失調症や躁鬱病の児童ではないのか。
診療上では、親の態度が恣意的だから、子が自己否定的に捉えるということが、客観性を阻害する主な原因とは言い難く、親子関係を修正しても摂食障害が改善しないことが多い。
どちらかというと子が元来、客観性の歪を生じる統合失調症や躁鬱病であり、しかも親が理解力や共感性がなかったり、親が統合失調症や躁鬱病等であり親側の客観性の維持が困難な場合に、結果として子供にアンビバレンツな影響を与え易いことはある。
ヒルテブルグの摂食障害の中核症状である自尊心の欠如は親子関係のみで成立するとは認め難い。
統合失調症や双極性における、客観性の低下、欠落こそが中核症状である。
つまり、子供の視線とそぐわない親の態度は子の客観性の発達を阻害することはあっても、これが摂食障害の主たる原因とは言い難い。
これは統合失調症や双極性障害の遺伝が多く、結果、負因のある親と遺伝を受けた子の関係が偶々、摂食障害の主因と考えやすかっただけではないか。
根本的に、統合失調症、双極性障害の患者は悲観的思考、被害的に思考に支配され自己否定的であり、自己主張は苦手である。
ストレスが蓄積しても、外に向かって発散し難く、内側に発散されることが多く、摂食障害もリストカットと同様に自傷行為といえる。
この様な、客観性の低下を認める状況下での親子関係の修正を主とするカウンセリングは、ある程度効果があってもそれは限定的と言える。
①拒食の病理
拒食は、ボデイイメージの障害や対人関係における、極端な被害的、自己否定的思考により形成される。これらの認知障害は妄想や幻覚とも、強迫症状とも考えることも出来る。
②過食の病理
過食は、ボデイイメージの歪というよりも、鬱状態の際に多いがイライラや自己不満足感の代償として、又は躁状態の際の食欲増進によって起きる。
簡単に説明すれば以下の様である。
①子供は自身に内在すべき自己規範が持てなくなり親の顔色見て行動するようになる。
②自分の視点にそぐわない親に対して愛情を感じることは出来ずに、怯えることとなる。
③この親に対する認知パターンは、他の対人関係にも波及することとなる。
子供の視線とそぐわない親の態度は確かに子の客観性の発達を阻害する可能性があるが、これが主たる原因だろうか。
元々、客観性の歪を生じる統合失調症や躁鬱病の児童ではないのか。
診療上では、親の態度が恣意的だから、子が自己否定的に捉えるということが、客観性を阻害する主な原因とは言い難く、親子関係を修正しても摂食障害が改善しないことが多い。
どちらかというと子が元来、客観性の歪を生じる統合失調症や躁鬱病であり、しかも親が理解力や共感性がなかったり、親が統合失調症や躁鬱病等であり親側の客観性の維持が困難な場合に、結果として子供にアンビバレンツな影響を与え易いことはある。
ヒルテブルグの摂食障害の中核症状である自尊心の欠如は親子関係のみで成立するとは認め難い。
統合失調症や双極性における、客観性の低下、欠落こそが中核症状である。
つまり、子供の視線とそぐわない親の態度は子の客観性の発達を阻害することはあっても、これが摂食障害の主たる原因とは言い難い。
これは統合失調症や双極性障害の遺伝が多く、結果、負因のある親と遺伝を受けた子の関係が偶々、摂食障害の主因と考えやすかっただけではないか。
根本的に、統合失調症、双極性障害の患者は悲観的思考、被害的に思考に支配され自己否定的であり、自己主張は苦手である。
ストレスが蓄積しても、外に向かって発散し難く、内側に発散されることが多く、摂食障害もリストカットと同様に自傷行為といえる。
この様な、客観性の低下を認める状況下での親子関係の修正を主とするカウンセリングは、ある程度効果があってもそれは限定的と言える。
①拒食の病理
拒食は、ボデイイメージの障害や対人関係における、極端な被害的、自己否定的思考により形成される。これらの認知障害は妄想や幻覚とも、強迫症状とも考えることも出来る。
②過食の病理
過食は、ボデイイメージの歪というよりも、鬱状態の際に多いがイライラや自己不満足感の代償として、又は躁状態の際の食欲増進によって起きる。
摂食障害の精神病理(女性性との関係)
極端なやせ願望あるいは肥満恐怖は客観性の歪の存在を示唆する。元々、女性は被観察対象としての自我を強く意識することが、男性とは相対的に異なる。
確かに男性が女性を外見で評価することは多く、肥満等の外見を強く意識することは正常と言える。
但し、極端なやせ願望は周囲からの評価を落とすことが自明であり、不健康な外見は男性だけでなく同性から見ても病的に印象付けることとなる。
極端なやせ願望あるいは肥満恐怖は、女性の外見に関する周囲からの評価を気にするという特徴を前提に、その不安が統合失調症や躁鬱病に代表される自明性の喪失や、間主観の喪失による客観性の歪によって極端に強迫的に妄想的に加工されたものと考えられる。
ボデイイメージの障害は上記のメカニズムで起こるものと考える。
確かに男性が女性を外見で評価することは多く、肥満等の外見を強く意識することは正常と言える。
但し、極端なやせ願望は周囲からの評価を落とすことが自明であり、不健康な外見は男性だけでなく同性から見ても病的に印象付けることとなる。
極端なやせ願望あるいは肥満恐怖は、女性の外見に関する周囲からの評価を気にするという特徴を前提に、その不安が統合失調症や躁鬱病に代表される自明性の喪失や、間主観の喪失による客観性の歪によって極端に強迫的に妄想的に加工されたものと考えられる。
ボデイイメージの障害は上記のメカニズムで起こるものと考える。
摂食障害の精神病理(他疾患との関係)
摂食障害、自傷行為、アルコールや薬物依存は密接な関係があるとされる。
衝動性や自罰的であることは双極性障害の急峻に発散されるエネルギー放出の傾向、統合失調症の自己否定的妄想的解釈、女性が本質的に持っている外部に対する暴力的エネルギー放出の困難さが関係しているのではないか。
又、アルコールや薬物依存に関しては、アルコールや特定の薬物が気分高揚作用があり、特に双極性障害患者はこの作用が顕著であり依存症となり易いと考える。
衝動性や自罰的であることは双極性障害の急峻に発散されるエネルギー放出の傾向、統合失調症の自己否定的妄想的解釈、女性が本質的に持っている外部に対する暴力的エネルギー放出の困難さが関係しているのではないか。
又、アルコールや薬物依存に関しては、アルコールや特定の薬物が気分高揚作用があり、特に双極性障害患者はこの作用が顕著であり依存症となり易いと考える。
摂食障害の治療
摂食障害の治療は精神療法、行動療法、認知療法、対人関係療法、家族療法等の精神療法が最も重要と考えられている。
現実と比較して極度に自己否定的な思考やボデイイメージの歪等の重度な場合、精神療法の効果は限定的である。
主流の精神療法は、客観性の歪が極度でないことを前提に、組み立てられるものであり、摂食障害は難治と言われるがこれは自明の理である。
当然、ベースとなる統合失調症や双極性障害を治療し客観性の歪を補正すべきである。
現実と比較して極度に自己否定的な思考やボデイイメージの歪等の重度な場合、精神療法の効果は限定的である。
主流の精神療法は、客観性の歪が極度でないことを前提に、組み立てられるものであり、摂食障害は難治と言われるがこれは自明の理である。
当然、ベースとなる統合失調症や双極性障害を治療し客観性の歪を補正すべきである。
そのほか
躁鬱(そううつ)病について
鬱病について
パニック障害について
統合失調症(自明性の喪失)について
不眠について
社会不安障害について
生理前症候群について
多重人格障害について
強迫性障害について
気分障害について
いじめ対策について
チック症について
摂食障害について
不登校と家庭内暴力
発達障害について