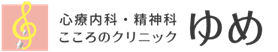多重人格障害の診断基準とは
これらの同一性、又は、パーソナリティ状態の少なくとも2つが反復的に患者の行動を統制している状態です。
重要な個人的情報の想起が不能であり、それは普通の物忘れで説明できない程強い事が必要です。
この障害は物質、または他の一般的身体疾患の直接的な生理学的作用によるものではない事が不可欠です。
解離の一形態
多重人格障害患者は人格の交代や健忘をしっかりと意識することは少ないと言えます。
これは、多重人格障害が人格の統一性の障害(自我意識障害)を引き起こし、時間的にも空間的にも自己の存在が不完全で不安定になるからです。
自分の時間的、空間的同一性を確保できなければ自分を確実に意識できない、客観視できないからなのです。
つまりこれは、解離を意味します。
つまり、多重人格に於ける人格は不完全で不安定なものであり、その人格を完成度の高いものとすることはその本質より不可能なわけです。
この、不完全な人格が、ある程度まとまった行動を起こす為には、他の人格の助けを借りなければならないことは多いと言えます。
従って、適応的行動を起こす際には、人格間の疎通性、協力が必要となるため、本来人格を分散させることにより精神的安定を図ろうとする(病的防衛機制である)多重人格化に逆行することにもなり多大なエネルギーが必要となる。
このことからも、多重人格化は究極の防衛機制(病的)と言えます。
自我脆弱性と防衛機制
個人的には被暗示性が強いというよりは、むしろ自我脆弱性が重度であると私は考えます。
この為、些細な刺激で解離、人格変化を起こすのです。
自我脆弱性は
解離と多重人格化は密接な関係があり、多重人格化を起こす分散した人格では、当然に空間的、時間的同一性を保てない為、解離している状況と言えます。
但し、解離を引き起こす人格は必ずしも多重人格化を引き起こすものではありません
自我の脆弱性のみでは多重人格化を引き起こすとは限らないのです。
窮地にたたされ、自己主張する他なくなった場合、幼児人格に退行したり、女性の場合には男性人格に変化して攻撃的になれることがあり、この方が楽なのです。
解離しただけではストレスから逃れられない状況下で、積極的に自己主張し易い人格にならざるを得ない場合に多重人格化するのです。
解離は行動すると言う意味では消極的で防衛機制ですが、多重人格化は何か行動しなければならない時の更に病的なやや積極的行動的防衛機制と言えます。
自我脆弱性の原因
多重人格化する要因として、最も大きいものはやはり個人の病的自我脆弱性が考えられます。
例えば、統合失調症の患者の場合、自明性の喪失、間主観性の喪失、客観性の歪により、ストレスを受けた際、過度に悲観的に被害的に捉えることとなります。且つそれが長期間に渡ることになる場合があります。
このことは鬱状態を悪化させ、更に認知機能の低下を招く悪循環に陥るのです。
何かストレスを受けた際に、ストレスを人一倍敏感に重く捉えPTSD(心的外傷症候群)として成立し易くなり、又解離しやすくなるのです。
又、自明性の喪失(簡単で自明のことがいきなり理解出来なくなったり、行えなくなったりする)、間主観性の喪失(客観的事実と思われる事象に基づいた主観、直感が持てなくなる)、客観性の歪により時間的、空間的同一性を失い「現実感がない」「自分が自分でない」という離人感、自我意識障害を生じ易くなります。
自我意識障害自体が既に解離していることであり、人格を分散化させてストレスに対応しやすい素地を持っていることになるのです。
解離性同一性障害の特徴
例えば、良くあることですが人格交代時「記憶がない」という場合が多いと思われます、実は記憶が残存している場合も少なくはないのです。
つまり、基本的には個人による解離のメリットとデメリットにより、どのような解離が起こるのかが決まるのです。
基本的に交代人格は現在の自分のメリットの為に出現しており、交代人格同志が必ずしもその存在に競合的であったり、争ったりするわけでもありません
但し、交代人格は不完全な人格であることは間違いない為、交代人格だけでは行動を起こすに不十分です。
前面に出現させた人格の背後に他の複数の人格が控えており、これらの人格間の調和を図ることが必要になることがあります。
解離性同一性障害の損益
苦しい自我(部分的)を、切り離すことにより一過性の内的安定を図ること。
自我同一性の極端な破壊を、自我同一性の拡散、不安定化によって一過性に防御すること。
外界に対して脆弱な統一的自我を拡散、攻撃的自我或いは自己主張的自我を出現させ、外交的(周囲に向かっての)防衛機制を行い、内向的(自分の中だけの)防衛機制で破綻した自己を保全すること。
外界に対して脆弱な統一的自我を拡散し、退行(未熟で幼稚)的自我を出現させることにより、周囲の理解を得て内向(自分の中だけの)的防機制で破綻した自己を保全すること。
解離のデメリットとしては以下のものが考えられます。
自我を拡散させるために統一的自我を失い、当然、自我同一性が失われること。
外界のストレスに対して客観的、理性的、状況適合的判断に基づいて行動を起こすことが困難となること。
人格間の調和を図る為には余分な精神的エネルギー、時間を費やすこと。
記憶の障害や状況適合的行動が困難になったり、時間がかかるため、当然に社会適応が困難となること。
解離することで社会的不適応を起こしたり、人前で解離することが自己評価を低下させ更に社会から逃避的となること。
解離が頻回に起こり自己評価の低下、社会的不適応が顕著になると、解離自体が大きなストレス要因となり、自我脆弱性は更に進行。病的防衛機制である解離を増々使用することになるという悪循環に陥ること。
解離性同一性障害の治療
自己の安心、安全を図る為の、環境調整や周囲の障害に対する理解を得る必要があります。
解離、多重人格は周囲には了解不能、怠慢と受けとられ易く、更に本人を窮地に追い込むことになり易いのです。
解離から強引に引き戻そうとしたり、人格を強引にまとめようとすることは、防衛機制(環境に適応するための自分なりの工夫)を強引に奪い取ることとなり、大きくストレスになります。
根本的に薬物療法は効果が少ないと考えられていますが、直接的効果が少なくても、上記の統合失調症、双極性障害、鬱状態を薬物療法で改善させることはとても重要であり、効果は十分に期待できます。
解離や、多重人格にならざるを得なくなった状況が改善し、合併する統合失調症、双極性障害、鬱状態を治療し、改善すると、解離や、多重人格等の病的防衛機制をとる必要がなくなる為、自然と改善してきます。
但し、解離や多重人格といった究極の病的防衛機制を取らざるを得なくなった状況を考慮すると、環境調整は不可欠であり、この環境調整が上手く行かなければ薬物療法の効果は限定的とも言えます。